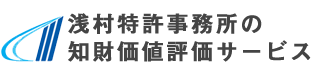コラム COLUMN
神奈川県、動産・知財の評価費用を補助する新制度「エコアセットかながわ」をスタート
更新日 : 2024.06.03
神奈川県は、2050年脱炭素社会の実現に向け、脱炭素に取り組む中小企業の動産や知的財産を融資に活かすため、6月3日から「エコアセットかながわ」という融資モデルを立ち上げました。金融機関と連携し、動産だけではなく、知的財産権の資産評価費用を補助(最大40万円)することで、経営者の個人保証に依存せず、事業性に着目した革新的な融資モデルを推進するものです。金融機関が県内の中小企業・小規模企業の事業価値に着目して融資に取り組むことを、自治体が後押しする狙いがあります。動産だけでなく知的財産権の評価費用まで対象にするこうした取り組みは、全国の自治体で初めてということです。
中小企業には資産評価費用の2分の1、小規模企業には3分の2を補助するものです(いずれも上限40万円)。この制度を利用できる企業は、脱炭素に取り組む中小企業・小規模企業に限られ、具体的には、再生可能エネルギー発電設備や省エネ設備などの導入企業、脱炭素関連の認証を受けている企業などが対象になります。
制度の仕組みはイメージ的には
① 脱炭素に取り組む中小企業から制度取扱金融機関への、融資の相談・申込み
② 中小企業から金融機関指定の評価機関への、資産評価の申込み・費用支払
③ 中小企業から金融機関への、資産評価結果の通知(企業と金融機関で結果共有)
④ 融資の実行
ということになります。
現時点での取り扱い金融機関は、横浜銀行、神奈川銀行、きらぼし銀行、静岡銀行、スルガ銀行の5行と、かながわ信用金庫、城南信用金庫の2信金の計7機関です。今後も増える見通しとのことです。
中国特許庁、特許評価ガイドラインを発表
更新日 : 2023.10.02
国家知的財産権局(中国特許庁)は、中国人民銀行、国家金融監督管理総局と共同で推奨的な国家標準として「特許評価ガイドライン」を制定しました。国家市場監督管理総局(国家標準化管理委員会)から公表の承認を受け、2023 年 9 月 1 日から実施するとのことです。
このガイドラインは、特許評価の基礎的な方法を提供するもので、特許の制度的特徴と運用規則を把握し、より総合的な評価指標とより科学的な評価方法を実現するよう指導するものだとのことです。このガイドラインは、初期に実施したパイロットプロジェクトと広範な協議に基づいて、特許価値分析と評価のための拡張可能で運用可能な一連の指標体系を構築しています。その中には、法的価値、技術的価値、経済的価値の3つの指標、二次的価値の14の指標、三次的価値の27の指標、および多数の拡張指標が含まれ、実施許諾・譲渡、財務・財政・税務、侵害救済、階層管理などの異なるシナリオに対して、指標の選択と重み付けの調整を科学的に導くというものです。 指標の選択と重み付けの調整は、企業、大学、科学研究機関、金融機関、評価機関などの主体が実際のニーズと具体的なシナリオに応じて選択するものであり、これに基づいて、交渉・折衝または総合的な市場情報分析を通じて、特許の市場価格と価値を実現することができるとされています。
https://mp.weixin.qq.com/s/SCJdRQyNVk2H6qYA5mPyjA
知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0の公表
更新日 : 2023.04.24
内閣府が「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」Ver1.0を公表したことは、すでにご紹介しましたが、このたび、同ガイドライン(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)のVer.2.0を公表しました。
2022年1月に公表された同ガイドラインのVer.1.0では、企業がどのような形で知財・無形資産の投資・活用戦略の開示やガバナンスの構築に取り組めば、投資家や金融機関から適切に評価されるかを示すものでした。
その後の企業・投資家・金融機関における意見や課題、国際的な環境変化等を踏まえ、本ガイドラインVer.2.0は、Ver.1.0で提示した5つの原則、7つのアクションに加え、企業と投資家との間の対話や情報開示の質を高めるためのコミュニケーション・フレームワークの概念を新たに付け加えたものとなっています。以下にそのフレームワークの概略を紹介します。
1.「事業ポートフォリオ変革からバックキャストした「ストーリー」上に戦略を位置付ける」
• 企業の事業ポートフォリオにおける各事業の成長性・資本収益性から見た現在の位置付け(As Is)を明確にし、目指すべき将来の姿(To Be)に到達するために、どのようなシナリオで事業の位置付けを引き上げていくのか。その際に、知財・無形資産戦略をどのように活用し、実現するのかを明らかにする情報開示や対話を行う。
バックキャスト、すなわち目指すべき未来から逆算して、知財・無形資産をどのように活用するかストーリーを立てて、投資家等に情報開示や対話を行うということです。
2.「自社の本質的な強みと知財・無形資産をビジネスモデルに接続する「企図する因果パス」を明らかにする」
• 「製品・サービスの競争力・差別化要因となる知財・無形資産が他社と何故どのように異なり、どのような時間軸で持続可能で競争優位なビジネスモデルに繋がるのか」、その実現性を含めて説明し、その投資戦略の優位性・必然性を明らかにする情報開示や対話を行う。
上記ストーリーを実現すべく、自社の知財・無形資産を今後のビジネスモデルの強みにどのようにつなげるのか、目標から成果までの因果関係・相関関係を明らかにして、投資家等に情報開示や対話を行うということです。
3.「目指すべき経営指標(ROIC 等)と知財・無形資産投資・活用戦略を紐付ける」
• 企業における知財・無形資産の投資・活用を、コーポレートレベルの経営指標(ROIC等)と紐付けて決定し、企業価値向上に対する知財・無形資産の投資・活用の貢献を明らかにする情報開示や対話を行う。
知財・無形資産を活用したり、それに投資することが、例えばROIC(投下資本利益率)などの経営指標とどのように紐付けられるのかを可視化等明らかにして、投資家等に情報開示や対話を行うということです。
上記の1.は2.と3.を包含した上位の概念として捉えることができます。2.の「企図する因果パス」を明らかにし、3.の経営指標との紐付けどのように紐づけられるのか明らかにして、1.のストーリー・シナリオを組み立てることが企業と投資家・金融機関間のコミュニケーションに重要だということのようです。
韓国特許庁、迅速かつ正確な価値評価システムを構築する
更新日 : 2023.03.10
韓国特許庁は、知財価値評価を知的財産・技術市場全般に拡散させるための戦略を本格的に推進するとのアナウンスをしました。
知財価値評価とは、知財の現在又は将来の価値を金額、等級等で算定することであり、近年知財を担保とした貸付、投資等の金融分野で活発に活用されています。ただし、知識財産金融の他にも、知的財産取引、特許侵害損害賠償および技術流出被害分析など様々な分野で知的財産価値評価が活用できるにもかかわらず、専門分野別価値評価モデルが用意されていないため、評価の信頼性に対する問題が提起されていました。
韓国特許庁は、2月24日(金)午後2時に韓国知識財産センター19階大会議室で、知的財産価値評価制度の問題点を検討し、解決策を練るための「知的財産価値評価拡散戦略専門家協議体」を発足しました。協議体では、産業界、法曹界、学界などの専門家が集まって取引、損害賠償、技術流出など専門分野別の価値評価の争点を発掘し、分野別知的財産価値評価モデルを開発するための研究方向を設定します。協議体から導き出された研究に方向に沿って、専門分野別の評価モデルを確立し、人工知能(AI)と専門家の評価を融合した新しい価値評価システムも構築していく計画とのことです。
韓国特許庁長官は「知的財産が企業成長のための投資などの金融分野で広く活用されるにつれて、知的財産価値評価市場も急激に成長している」とし、「韓国特許庁は今年を価値評価システム確立の元年とし、価値評価を知的財産と技術市場全般に普及させるために努力する」と述べました。
簡易知財価値評価ツール AIVAS-FREE TRIALのご提供について
更新日 : 2022.12.07
弁理士法人 浅村特許事務所 (所在地:東京都品川区、代表者:浅村 昌弘) は、知的財産の金銭的価値を簡易に評価するためのツールAIVAS-FREE TRIALの提供を2022年12月 1日に開始いたしました。特許番号等を入力するだけで知財価値の金銭的評価ができる簡易ツールです。本件につき12月 2日にプレスリリースを行った結果、総計30広告媒体にて掲載されました。
昨今、M&A、経営戦略、融資判断などにおいて知的財産の占める割合がますます高まっており、知的財産の金銭的な価値を確認することが企業にとって必須となっています。ただ、自社の特許権にコストと時間をかけて価値評価するだけのメリットがあるか不明な状況では、なかなか知財の価値判断をすることに踏み切れないのが実情です。
そのため浅村特許事務所は、このたびお客様ご自身が所有する特許権の金銭的価値を簡易に評価できる新しいツールAIVAS-FREE TRIALの提供を開始いたしました。
出願番号や予想売上などの簡単な入力を行うだけで、瞬時に特許権の評価額を算出することができます。
なお、実際の知財価値評価は、製品の市場や発明の技術評価など様々な情報に基づいて緻密に行う必要があります。
AIVAS-FREE TRIALは、お客様の特許権がそのような緻密な評価を行う価値があるかどうかを判断するための参考情報をご提供することを目的とするものです。
AIVAS-FREE TRIALでご提示した評価額について、浅村特許事務所は一切責任を負いかねますので、その旨ご了承の上でご利用ください。
■「AIVAS-FREE TRIAL」について
(1)知財金銭的価値簡易評価ツール AIVAS-FREE TRIAL提供アドレス
https://aivas.jp/freetrial
(2)評価手法
発明を実施している場合若しくは実施予定がある場合はインカムアプローチにより、実施していない場合はコストアプローチにより、自動的に特許権の評価額を算出し提示します。
(3)利用料
無料です。いつでも、どなたでも、何件でも自由に利用することができます。
(4)より緻密な金銭的価値評価のご提供
AIVAS-FREE TRIAL は簡易価値評価ツールです。
〇 特許出願中の発明の金銭的価値算出
〇 特許発明のより詳細な金銭的価値の算出
〇 複数特許発明全体としての金銭的価値の算出
〇 意匠権の金銭的価値算出
〇 商標権の金銭的価値算出
〇 著作権の金銭的価値算出
〇 複数の知的財産(例えば、特許発明と登録商標)の総合的知財価値評価
〇 企業が有する知的財産の総合知的財産金銭的価値評価
等、広く知的財産全般のより緻密な金銭的算出が必要な場合については、
浅村特許事務所知財価値評価サービスチームが個別に対応いたしますので、ご相談ください。
知的財産価値評価に関するご依頼、ご質問等は、お気軽に浅村特許事務所 知財価値評価お問い合わせ窓口までご連絡ください。
心よりお待ちしています。
ARCHIVES
- 2024年6月
- 2023年10月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2022年12月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
![TEL: 03-5715-8651[受付時間:平日9:00?17:00]](/images/tel.png)